ボールねじの種類にはどんなものがありますか
JIS規格でのボールねじ種類の区分は、位置決め用と搬送用との2つに大別され、その各々に精度等級としてクロダでは位置決め用としてC0級~C5級と、搬送用ではC7級、C10級に区分されています。
精度に関する詳細につきましては、『ボールねじの精度等級について知りたい。』にも掲載していますので、そちらも合わせてご覧ください。
規格では特に製造方法についての決まりはありませんので、どのような方法で製造しても良いこととなります。
ボールねじの主要部品は、ねじ軸・ナット・鋼球循環部品と鋼球となりますが、この中で特にねじ軸の製造方法によって、代表的な2つの種類として『転造ボールねじ』と『研削ボールねじ』がありその2つの特徴について示します。
転造ボールねじ
成形方法
転造ボールねじのねじ軸は、丸棒状の鋼材を回転させながら転造ダイスと呼ばれる工具によりねじ溝を成形する方法です。
転造ダイスは、外周にねじ溝と逆形状の凸形の複数の山形からなり、一対の転造ダイスに鋼材を押し当てねじ溝を成形します。
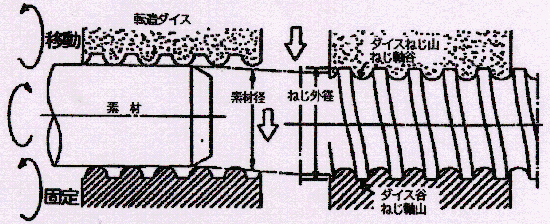
ねじ軸の外観
ねじ軸の外観にはシーミングと呼ばれる筋が見られます。(軸とリードの組み合わせにより見え難いものもあります。)
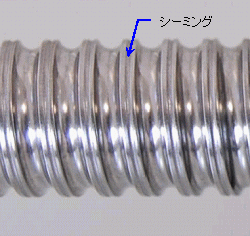
製造工程(概略)
転造 → 熱処理 → 端末加工
リード精度
上記に示す『転造→熱処理』の工程で目標精度に仕上げるため一般的には次に示す精度等級となります。
C7級、C10級
軸方向すきま
転造品では、ねじ軸の円筒度が研削品と比較し若干劣るため、軸方向すきまを極端に少なくしたり、0(ゼロ)にした予圧品では良好な作動性が得られない場合があるため、一般的な軸方向すきまは0.03~0.20mm程度に設定されています。
ナットの組合せ方式
一般的には、シングルナットとなります。
研削ボールねじ
成形方法
研削ボールねじのねじ軸は、丸棒状の鋼材に切削バイトや研削砥石でねじ溝を削り製造する方法です。
ねじ軸の外観
ねじ軸の外観は、軸の外周部は円筒研削により加工されておりなめらかな形状です。
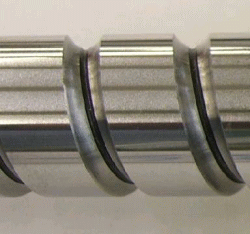
製作工程(概略)
軸外観形状の成形加工 → 熱処理 → 円筒研削 → ねじ溝研削 → 端末加工
リード精度
研削ボールねじでは、転造ボールねじとは異なり熱処理後の工程での精度出しができるため高精度から低精度まで製作できます。
C0級、C1級、※C2級、C3級、※C4級、C5級、C7級、C10級
※印の等級は、KURODA独自の規格となります。詳細につきましてはカタログをご覧ください。
軸方向すきま
研削品では、ねじ軸の円筒度を安定的に製作できるため、軸方向すきまのあるものでは0.005~0.20mmと予圧品の製作が可能です。
ナットの組合せ方式
研削品では下記に示すものが製作可能です。
- シングルナット
- ダブルナット
- インテグラルナット
上記の組合せ方式についての詳細は、『ボールねじのシングルナット、ダブルナット、インテグラルナットの違いについて教えてください。』に掲載していますのでそちらもご覧ください。
